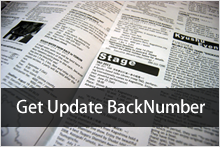**************** 目次 ****************
二十四節気って何? 雑節って?
1年は4つの季節に分けられますが、日本ではさらに細かく1年が二十四に分けられていて、二十四節気(にじゅうしせっき)と呼ばれています。
以前、ほとんどの人にとって農業が大切な生活の一部だった時代には、自然と密接に関係した生活のなかで、いつ田畑を耕し、いつ種まきをするのかといった目安が必要でした。
その目安として考え出されたのが二十四節気(にじゅうしせっき)と雑節(ざっせつ)です。

二十四節気の起源は中国です。
中国においても、昔の人々は実際の季節の移り変わりを正確に知るすべが必要でした。そのため二十四節気が考え出されました。
それが日本に伝わったのは6世紀のことだそうですが、中国の四季と日本の四季とにはずれがある場合もあります。
そこで、季節の移り変わりをより的確につかむために二十四節気に日本独自の雑節が加えられました。そのため、雑節も農作業に関連していることがら多いです。
季節の移ろいの目安
現代では、クリスマスや冬休み、バレンタインデーに卒業式や入学式と様々なイベントがあります。そういったものがなかった時代、人々は節句、二十四節気、雑節を季節の目安にしていました。
節句は5つ。
二十四節気は24。
そして、雑節には節分,土用(春夏秋冬4回)、彼岸(春秋),社日(春秋)、八十八夜,入梅,半夏生,二百十日、二百二十日があります。
二十四節気それぞれの意味と2023年の二十四節気
二十四節気につけられた名前はそれぞれの季節やその季節の自然の様子を漢字二文字で表す風情のあるものだと感じます。
以下に二十四節気とその意味、2022年の二十四節気がそれぞれ何月何日に当たるかをまとめました。
2023年 (令和5年) の二十四節気
|
二十四節気における季節 |
二十四節気における月 |
No. |
節気 |
意味 |
月日 |
|
春 |
1月 |
1 |
春の兆しが見え始めるころ |
2月4日 |
|
|
2 |
雪が雨に変わり、氷が見ずに変わるころ |
2月19日 |
|||
|
2月 |
3 |
冬ごもりをしていた虫たちが土の中から出てくるころ |
3月6日 |
||
|
4 |
昼と夜の長さがほぼ同じになる日 |
3月21日 |
|||
|
3月 |
5 |
すがすがしく明るい空気が満ちるころ |
4月5日 |
||
|
6 |
穀物を成長させる雨が降るころ |
4月20日 |
|||
|
夏 |
4月
|
7 |
夏の兆しが見え始めるころ |
5月6日 |
|
|
8 |
植物が茂り、天地に満ち始めるころ |
5月21日 |
|||
|
5月
|
9 |
麦や稲など帆の出る植物の種をまくころ |
6月6日 |
||
|
10 |
1年でもっとも昼が長い日 |
6月21日 |
|||
|
6月
|
11 |
暑さがどんどん増していくころ |
7月7日 |
||
|
12 |
1年でもっとも暑いころ |
7月23日 |
|||
|
秋 |
7月
|
13 |
立秋 |
秋の兆しが見え始めるころ |
8月8日 |
|
14 |
暑さが和らぐころ |
8月23日 |
|||
|
8月 |
15 |
夜の温度が下がり、朝露が降りるころ |
9月8日 |
||
|
16 |
秋分 |
昼と夜の長さがほぼ同じになる日 |
9月23日 |
||
|
9月 |
17 |
寒露 |
草花に冷たい露が宿るころ |
10月8日 |
|
|
18 |
霜降 |
霜が降り始めるころ |
10月24日 |
||
|
冬 |
10月
|
19 |
立冬 |
冬の兆しが見え始めるころ |
11月8日 |
|
20 |
小雪 |
雪が降り始めるころ |
11月22日 |
||
|
11月 |
21 |
大雪 |
雪が激しく降り始めるころ |
12月7日 |
|
|
22 |
1年でもっとも夜が長い日 |
12月22日 |
|||
|
12月 |
23 |
小寒 |
寒さが厳しくなり始めるころ |
1月6日 |
|
|
24 |
大寒 |
1年でもっとも寒い時期 |
1月20日 |
雑節それぞれの意味と2022年の雑節
季節をより正確につかむために、二十四節気に加えて考え出されたのが日本独自の雑節です。
二十四節気や雑節を季節の目安として自然とともに生きた先人たちの暮らしが垣間見えるようです。
2023年 (令和5年) の雑節
|
雑節 |
意味 |
月日 |
| 立春の前の18日間 *季節の変わり目の目安 |
1月17日~2月3日 |
|
| 季節を分ける日で冬の終わり。 *本来は春夏秋冬の4回。 |
2月3日 |
|
| 春分の日をはさむ前後3日間の7日間 (先祖のお墓参りや仏壇にぼた餅を備えるのは日本独自の風習) |
3月18日~3月24日 |
|
|
春の社日 |
春分に近い戊(つちのえ)の日。 土地の神様(産土神)を祀って豊作を祈る日。 |
3月21日 |
| 立夏の前の18日間 *季節の変わり目の目安 |
4月17日~5月5日 |
|
| 立春から88日目。 農作業を始める日の目安。 |
5月2日 |
|
| 梅雨に入るころ |
6月11日 |
|
| 半夏(烏柄杓)という薬草が生えるころ。あるいは、ハンゲショウ(カタシログサ)という草の葉が半分白くなって化粧しているようになるころ。 田植えを終えるころの目安。 |
7月2日 |
|
| 立秋の前の18日間 *季節の変わり目の目安 |
7月20日~8月7日 |
|
|
二百十日 |
立春から数えて210日目。 台風がくるころで農家の厄日。 |
9月1日 |
|
二百二十日 |
立春から数えて220日目。 二百十日とともに台風が来るころで農家の厄日。 |
9月11日 |
| 秋分の日をはさむ前後3日間の7日間 (先祖のお墓参りや仏壇にぼた餅を備えるのは日本独自の風習) |
9月20日~9月26日 |
|
|
秋の社日 |
秋分に近い戊(つちのえ)の日。 土地の神様(産土神)を祀って五穀豊穣を感謝する日。 |
9月27日 |
| 立冬の前の18日間 *季節の変わり目の目安 |
10月21日~11月7日 |
デジタル化が進み、土と触れ合う生活がますます遠くなってきているように感じる昨今ですが、二十四節気や雑節を意識して暮らすことで季節の移り変わりをもっと身近に感じられるかもしれません。
タグ : 2021年 , Free Wi-Fi , Nen , ねん , ひなまつり , アトリエ , エコバッグ , カフェ , ガーデン , クリスマス , ケーキ , コーヒー , フォーマル , フリーWi-Fi , 令和3年 , 公共無線LAN , 公共無線ラン , 千本いちょう , 春の木市 , 無 , 無料Wi-Fiスポット , 癒し , 秋 , 紅茶 , 紅葉狩り , 行楽 , 避難所 , 防災 , 雛祭り , 風呂敷 , 鹿児島















![[観光農園] ひむかの郷](http://kic-update.com/engine/assets/d7a94a9cb2d6a588992f3f0d5b8891362-150x150.jpg)