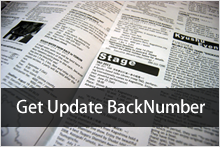***目次***
年に4回ある土用
土用の起源
土用にまつわる行事と風習
土用の虫干し
土用干し
土用三郎
土用期間にやってはいけないと言われていること
土用の間日
昔の知恵。恐れず賢く現代に生かして
年に4回ある土用
「土用」と聞くと「土用丑の日」を思い浮かべる方が多いと思います。そのためか夏のイメージが強いですが、実は土用は年に4回あります。

それぞれ、立春、立夏、立秋、立冬の前18日間の期間です。立春前が「冬の土用」で1月17日ごろに始まり、立夏前が「春の土用」で4月17日ごろ、立秋前が「夏の土用」で7月20日ごろ、立冬前が「秋の土用」で10月20日ごろに始まります。
*土用期間は年によって異なります。
*土用の入りの日によっては18日間でない場合もあります。
2024 (令和6)年の土用期間
冬土用: 2024 (令和6)年1月18日 (木) ~2月3日 (土)
春土用: 2024 (令和6)年4月16日 (火) ~5月4日 (土)
夏土用: 2024 (令和6)年7月19日 (金)~8月6日 (火)
秋土用: 2024 (令和6)年10月20日 (日) ~11月6日 (水)
なお、2024 (令和6)年の土用丑の日は7月24日 (水)と8月5日 (月)です。
土用丑の日についてはこちらをご覧ください。
土用の起源
土用は中国から伝わった「陰陽五行思想」に基づいています。
陰陽五行思想では、自然界は木・火・土・金・水の5つの要素から成り立っていると考えます。季節もこの5つの要素に当てはめて、春は木、夏は火、秋は金、冬は水の気と考えられました。そして、土は季節の変わり目である立春、立夏、立秋、立冬の前18日間に割り当てられました。この時季は土の気が盛んになるとされ、「土旺用事」と呼ばれ、それが「土用」となりました。
土用にまつわる行事と風習
季節の変わり目に当たる土用。それにまつわる行事や風習も残されています。
土用の虫干し
梅雨明けのころにやってくる夏土用。湿気やカビ、虫が気になるころです。
そこで、害虫やカビなどから衣類や本を守るために行われるのが「土用の虫干し」です。晴れた日が続いた乾燥した日に風通しの良い場所に陰干しをして風を通します。
昨今はエアコンや除湿機のおかげでこのような手間のかかることをする風景は見られなくなりましたが、寺院では今でも行っているところがあり、虫干しを兼ねて本尊などを特別に拝観できたりするそうです。
土用干し

田舎のおばあちゃんお手製の梅干しが毎年送られてくるというご家庭もあるのではないでしょうか? また、健康や食への関心が高まっている昨今、ご自分で梅干し作りに挑戦する方も増えてきているようです。
その梅干しづくりに欠かせないのが土用干しです。土用干しをすることで殺菌作用が働いて長期保存が可能になります。また、果肉が柔らかくなり、色も鮮やかになって風味が増し、味もまろやかになります。
この土用干しをするのも7月下旬から8月上旬ごろの夏土用のころです。
土用三郎
「土用三郎」。耳慣れない言葉ですが、これはその年の豊作を占うことです。また、その日を擬人化した言い方でもあります。
夏の土用に入ってから三日目のことで、この日が晴れなら豊作、雨だと凶作と言われています。
これと似た風習に彼岸太郎、八専次郎、寒四郎と呼ばれるものがあります。彼岸の一日目、八専の二日目、寒の四日目のことで、この日が晴天だとその年は豊作と言われます。
*「八専」というのは、日の干支が壬子(甲子から数えて49番目)から癸亥(同60番目)の間の12日間のうち、干・支ともに同じ五行となる壬子、甲寅、乙卯、丁巳、己未、庚申、辛酉、癸亥の8つ
*「寒四郎」の「寒」は、寒の入りのこと。
土用期間にやってはいけないと言われていること
土動かし

土用期間中は、土公神(どくしん・どこうしん)という陰陽道の土をつかさどる神様が支配するとか、土の中にいらっしゃると言われています。この期間は土を動かしてはいけないとされています。
土を動かすというのは、土いじり、草むしり、柱立て、基礎工事、壁塗り、井戸掘りなどを含む穴掘り、増改築などです。
なお、土用前に着手した農作業や増改築についてはやってもよいと言われています。
新しいこと
土用期間中は、転職、就職、結婚、結納、開業、開店、新居購入などの新しいこともしてはいけないと言われています。
土用はそれぞれの季節の変わり目にあたります。この時季は体調を崩しやすいものです。
昔は医学が発達していなかったため、体調の変化が生活に大きな変化を与えたり、病気が重くなったりしまいた。
そのために土用の期間中は新しいことは始めず、養生して過ごすようになったため、以下のことをしないという風習ができたのかもしれません。
旅行
おそらく体調を崩しやすい時季、昔は医学が発達していなかったという同じ理由からだと思いますが、土用期間の旅行もよくないとされています。
土用の間日
一年間に4回も18日間ずつある土用。その期間にこんなにも禁忌があるなんて大変です。
近年では、そんなこと気にしない、土用の禁忌を知らないという方がほとんどではないでしょうか。しかし、自然とともに暮らしていた昔にあって、自然や神を畏れ、敬っていた人々にとっては無視できない期間だったことと思います。
そこで、「土用の間日」と呼ばれる日があります。この日は土公神が天上に行く日で土を離れるので、土を動かしても問題がないと言われています。
20224 (令和6) 年の土用の間日
冬土用の間日
2024 (令和6) 年1月18日(木) 巳・1月27日(土) 寅・1月28日(日) 卯・1月30日 (火) 巳
春土用の間日
2024 (令和6) 4月23日(火) 巳・4月24日(水) 午・4月27日(土) 酉
夏土用の間日
2024 (令和6) 7月19日(木) 申・7月26日(金) 卯・7月27日(土) 辰・7月31日(水) 申
秋土用の間日
2024 (令和6) 10月22日(火) 未・10月24日(木) 酉・10月26日(土) 亥
11月3日(日) 未・11月5日(火) 酉
*それぞれの間日のあとに記載してある干支は、陰陽五行説に基づいて月日に当てられている干支の名前です。今年の干支である「辰年」もこの陰陽五行説に基づいています。
土用の間日は季節によって次の干支日が間日になるとされています。
冬土用の間日:寅・卯・巳の日
春土用の間日:巳・午・酉の日
夏土用の間日:卯・辰・申の日
秋土用の間日:未・酉・亥の日
昔の知恵。恐れず賢く現代に生かして
現在では土用といえば「うなぎ」。でも、こうしてひも解いてみると昔の知恵と結びついた深い風習が存在することが分かります。
「これやっちゃいけないんだ」と恐れるのではなく、体調を崩しやすい時季であることを自覚してふだん以上に節制したり、虫干しなどの昔の知恵を拝借して、クローゼットに風を通したりして快適で健康に過ごしす時期なのだととらえましょう。
タグ : 2021年 , Free Wi-Fi , Nen , ねん , ひなまつり , アトリエ , エコバッグ , カフェ , ガーデン , クリスマス , ケーキ , コーヒー , フォーマル , フリーWi-Fi , 令和3年 , 公共無線LAN , 公共無線ラン , 千本いちょう , 春の木市 , 無 , 無料Wi-Fiスポット , 癒し , 秋 , 紅茶 , 紅葉狩り , 行楽 , 避難所 , 防災 , 雛祭り , 風呂敷 , 鹿児島














![[観光農園] ひむかの郷](http://kic-update.com/engine/assets/d7a94a9cb2d6a588992f3f0d5b8891362-150x150.jpg)