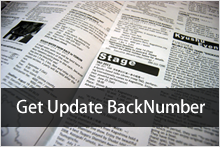秋になると野山に日の光を受けてススキが銀色に輝くようになります。
このススキ、秋の七草の一つだということをご存知ですか?
別名を尾花といいます。
秋の七草は春の七草と違い、 何かの行事に関連するものではありませんが、私たちの生活には深く根ざし、食べものとして、あるいは薬としてお世話になっている植物です。
また、「七草」はもともとこの「秋の七草」を指し、山上憶良が詠んだ歌に由来する、というからずいぶん古くから親しまれているんですね。
萩の花 尾花 葛花 瞿麦の花 姫部志
(はぎのはな おばな くずはな なでしこのはな おみなえし)
また藤袴 朝貌の花 (また ふじばかま あさがおのはな)
*最後の「朝顔の花」については諸説あるようですが、「桔梗」説がもっとも有力とされています。
ちなみに山上憶良は奈良時代初期の貴族であり『万葉集』には78種もの歌が撰ばれている歌人です。
野に咲く名も知らない草花たちでも、名前を知ったら、なんだか親しみがわき、特別な花になった。そんな経験ありませんか?
秋の七草を覚えて、特別な草花にしちゃいましょう。
そして、万葉の世界に思いを馳せてみてもいいかもしれません。
注:秋の七草を萩、すすき、葛、撫子、木槿、桔梗、昼顔とする説もあります。

萩(はぎ)
秋の野山に揺れる萩。花は蝶に似た小さい花で、紅紫色、白などがあります。秋のお彼岸に備えるあんこのお餅「おはぎ」は、この花が咲く時期であることから着いた名前です。ちなみに同じ食べものでも春のお彼岸は、牡丹が咲く時期であることから「ぼたもち」と呼ばれます。

尾花(おばな)
「幽霊の正体見たり枯れ尾花」は、幽霊だと思っていたら枯れたすすきだったというように、薄気味悪いと思っていたものも確かめたら怖いものではなかったということわざですが、この「尾花」がすすきです。秋の日を受けて輝くすすきはとても美しいですね。
また、すすきはお月見には欠かせないですね。

葛(くず)
マメ科の植物でつるを伸ばして木などに巻き付き、勢いよく増えます。花はチョウのような形をした紫色で、二十センチぐらいの房状につきます。
木を枯らしてしまうこともあるので迷惑がられる植物ですが、食用や薬として利用されてきました。
葛粉はこの植物の根からとれるデンプンを精製して造られます。お菓子の生地や料理にとろみをつけたり、体を温めるために飲んだりするのに用いられます。
胡麻豆腐の材料は大豆ではなく、この葛粉を使います。
また、漢方薬の葛根湯にはその名の通り、麻黄や甘草などとともに葛の根が使われています。

撫子(なでしこ)
夏から秋にかけてピンク色のかれんな花を咲かせる撫子にはヤマトナデシコという異名もあります。「やまとなでしこ」と言えば、日本人女性の理想の姿とされています。ー穏やかで美しく、清楚で男性をたてる女性。それでいて、芯は強く凛としている。
そんなイメージでしょうか?
実は10世紀にはすでに女性を撫子にたとえるようになっていたと言われています。
撫子ははかなげで美しい花ですが、乾燥に強くたくましい花です。
また、撫排尿作用があることから、漢方薬に使われています。

女郎花(おみなえし)
夏の山野に黄色い花を咲かせる女郎花。小さな花が茎の先端で幾つかに別れて咲きます。
なぜ秋の七草に「女郎」花が入っているの? と思われた方はいませんか?
女郎と言えば、江戸時代の遊女と思いがちですが、もともとは「女郎(おみな)」は若い女性を女性、あるいは女性を指す言葉でした。
この花が女郎花と呼ばれるようになったのは、美女を圧倒するほど美しかったからという説があります。
利尿、解毒、排膿などに効果があることから漢方薬にも使われています。

藤袴(ふじばかま)
川岸の土手などで秋に淡紅色の小さな花を咲かせます。
かの『源氏物語』にも登場する花であり、平安時代の衣服の襲(かさね)の色の名前にも「藤袴」というものがあり、裏も表も紫色です。
藤袴には利尿、解熱などの薬として漢方薬に使われます。

桔梗(ききょう)
山野で紫色の花を風に揺らす桔梗を目にすると秋だなあと感じますよね。風船のようにふくらんだ蕾も可愛い花です。
桔梗も平安時代の衣服の襲(かさね)の色の名前にあります。表は二藍、裏は青です。
この桔梗も咳を鎮め,排膿を促す働きがあるので、漢方薬としてよく使われています。
昼顔と木槿を秋の七草に加える説もあるので、ご参考までに画像をご覧ください。

昼顔(ひるがお)
野原などに咲く花で朝顔に似ていますが、朝顔が朝だけ咲いているのに対して昼顔は朝から夕方にかけて咲き、昼にも花を開いています。
昼顔は、葉、花、茎、根のすべて食べることができ、癖のない味で葉はお浸し、あえ物、天ぷら、炒め物、花はサラダや酢の物、汁の実、根はかき揚げや佃煮などで食べます。

木槿(むくげ)
「東洋のハイビスカス」とも呼ばれる木槿は、奈良時代に中国から渡来したと言われています。花は白、ピンク、紫など様々な色があります。
ハイビスカスとは花の真ん中から出ている花柱で見分けることができます。ハイビスカスはすらりと伸びた花柱の先に黄色い花粉がついているのが見えますが、木槿は太い花柱の下から上までおしべがつき、ハイビスカスよりもふわふわして白っぽく見えます。
この機会に秋の七草を覚えて、野山でその可憐さや古人に思いを馳せてみてはいかがでしょうか?
タグ : 2021年 , Free Wi-Fi , Nen , ねん , ひなまつり , アトリエ , エコバッグ , カフェ , ガーデン , クリスマス , ケーキ , コーヒー , フォーマル , フリーWi-Fi , 令和3年 , 公共無線LAN , 公共無線ラン , 千本いちょう , 春の木市 , 無 , 無料Wi-Fiスポット , 癒し , 秋 , 紅茶 , 紅葉狩り , 行楽 , 避難所 , 防災 , 雛祭り , 風呂敷 , 鹿児島















![[観光農園] ひむかの郷](http://kic-update.com/engine/assets/d7a94a9cb2d6a588992f3f0d5b8891362-150x150.jpg)